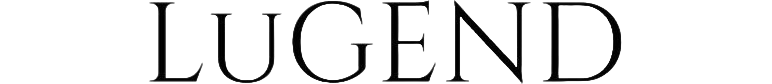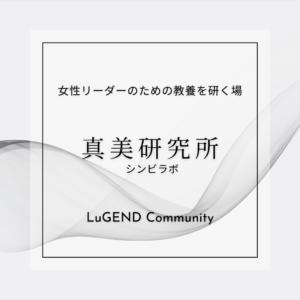こんにちは、真美研究所主宰の豊田ふみこです。
今日は、メルマガにてお伝えしたことをこちらでも紹介したいと思います。
西洋と東洋の知の構造の違い
私たちの多くは「新しい知識を得ることが人生を良くする」。そう信じています。
これは、自分は何も知らないという「無知」からスタートし、知らないから新しい知識が必要だという前提で、知識を積み重ねる西洋的な発想です。
一方で、東洋的な考え方は、「既に知っている」「知らないということがない」「それを思い出すだけ」というのが根底にあります。
なので、それを「思い出した」ときに得られる安定感や地に足がついた感は、どんどん更新されて終わりがない西洋的な学び方で得られる知識とは全く異なるものです。
このように、西洋と東洋では、知の構造が根本的に異なっています。

世界の知の構造を知る
しかし現代は、西洋の発想に支配されており、東洋的な発想の存在感は失われています。
ただ、受講生さん達とお話していると東洋的な考え方の方がしっくりくるとおっしゃる方が最近増えたように感じます。文字通り「思い出してきた」のかもしれません。
私自身も東洋思想を学び始めて7年、西洋哲学を学び始めて4年になりますが、一方から見ていただけではわからなかったことが、両方の知の特徴を知り俯瞰することで、世界や人に対する見方が大きく変わってきました。
そして、東洋の知恵は、私たちが世界や人間をどう理解し、どのように関わるかを根本から変える可能性を秘めています。これは、世界のトップリーダーや富裕層の方達がこぞって、日本の知である禅に興味を持つ理由でもあります。
知の構造を知ることで、世の中を俯瞰するように見るとあふれる情報に踊らされることなく、地に足をつけてビジネスも人生も送ることができます。