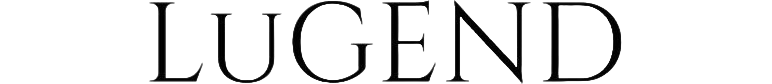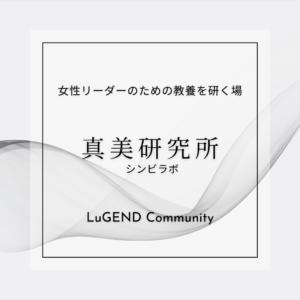こんにちは、真美研究所主宰の豊田ふみこです。
今日は、真美研究所にてお伝えした内容の一部をお話したいと思います。
「文学は美的距離を生じさせる」
これは、どういうことでしょうか?
文学こそが芸術の代表
美学の世界には「文学こそが芸術の代表である」という主張もあります。
目に見えない美的なものを表現する文学こそ、最も優れた芸術であるという考えです。
実際、造形による芸術が感性に直接訴えるにしろ、私たちはそこに色や形だけを見ているわけではありません。
そこに表現されている別の「何か」も見ています。
詩文学は美的対象としての芸術
例えば、哲学者カントは「想像力に訴える文学は、より豊かな美の表現を可能にする」と評価しています。
また、古代ギリシアの時代にさえ、すでに「詩(文学)は美的対象としての芸術」という考え方はありました。
アリストテレス曰く、表現手段が音、色や形、あるいは言葉かによって区別されるが、音楽、絵画、詩はすべて「模倣」であると。
ここでいう「模倣」とは、人間の感性に何かを訴えるもの、そうした特別な行動や感情を再現することを意味しています。
特に詩をはじめとする文学は、人間の行動や感情を再現しながらも、単に人物を真似してなぞるようなものではありません。
むしろ文学とは、混沌とした現実世界にひそむ類似性や関連性を見いだし、一連の出来事を秩序立てて構成するもの。
だからこそ、文学は現実以上に理解できる「物語」の世界を出現させます。

文学と哲学の違い
一方で、文学は哲学と違って、その目的は私たちにとって何らかの「快さ」を生み出すことにあるとされています。
例えば、悲劇という文学は、憐れみと恐れを通して、そうした種類の感情の浄化(カタルシス)を達成するものです。
ここで、文学の目的が快さにあるならば、物語の理解しやすさは、それを味わうための前提となります。
悲劇であれば、理解し共感するからこそ、登場人物に憐れみと恐れを感じるのであり、カタルシスによる快さが生じる。
また、文学が作り出すこうした世界は虚構にすぎませんが、物語は独自の構造を備え、読者に対して現実以上の説得力を持ちます。
このように、文学が虚構であることは「美的距離」を生じさせるのです。
聖なる空間
実物を見るのは苦痛であっても、それをこの上なく正確に模倣した似像を見ることを私たちは好みます。
文学の物語が現実ではないという潜在的な意識が、読者と作品の間に心理的な距離を作り出す。
ゆえに、現実においては目を背けるような出来事であっても、文学作品の中であれば見ることができる。
文学は私たちが出来事を安全に鑑賞できる「聖なる空間」であり、そこではありえないような感情体験が可能になります。
ちなみに、美学において「美的距離」は、美の対象としての芸術を鑑賞するための根底にある条件とされています。
美的距離のある態度
さて、これらをビジネスや人生に落とし込み考えてみるとどうでしょうか?
私たちはつい自分を基準にして、何かを人に教えようとしたり、わかってもらおうとします。
もしくは、相手が抱えている問題を解決してあげようとする。
それは、「美的距離」のある態度といえるでしょうか。
こうした点を踏まえると、「美的距離」のある態度こそ、真の誠実さといえるのではないでしょうか。