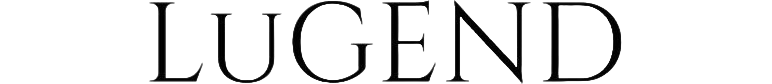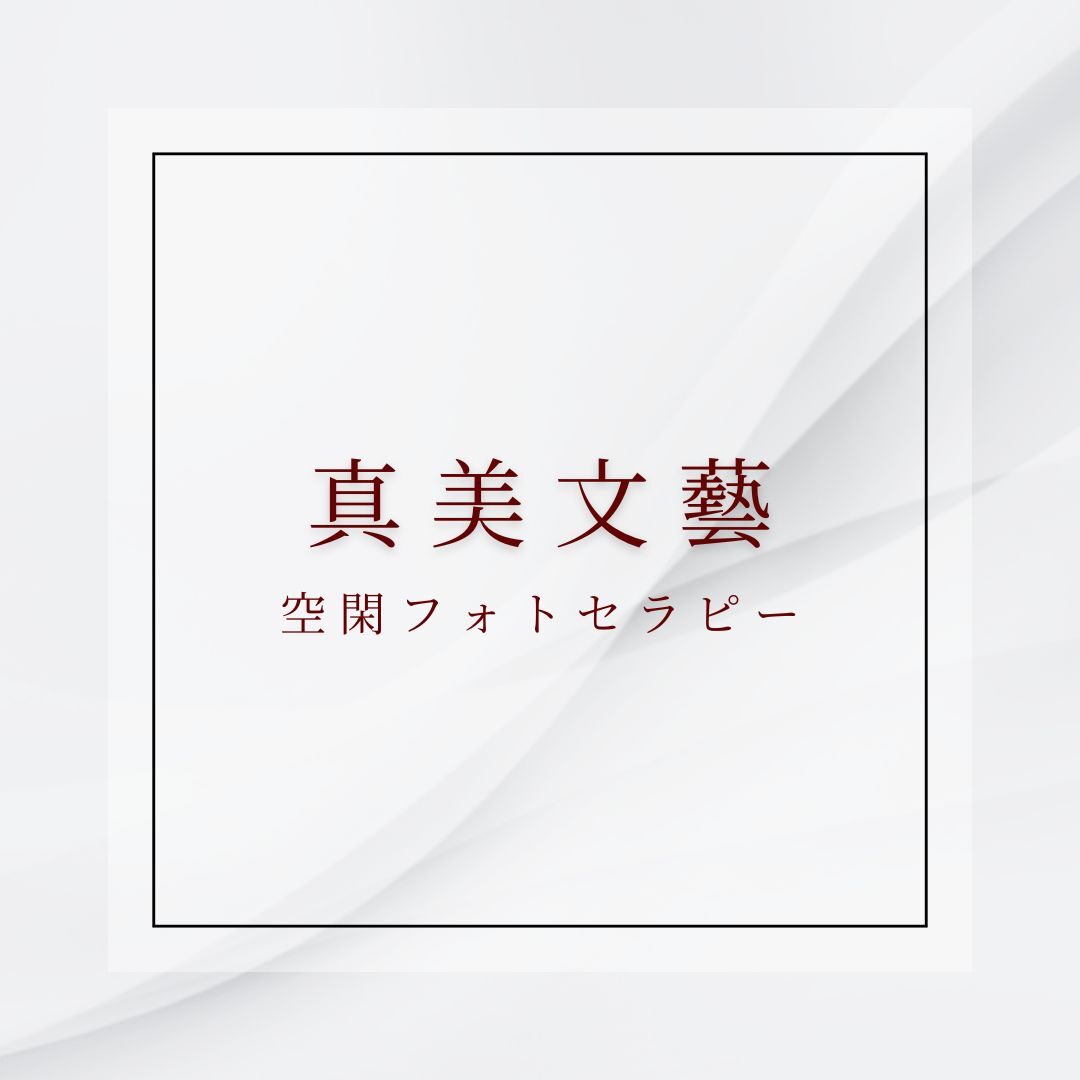女性リーダーのための教養を磨く場
「真美研究所」
美を求めてきた人がたどり着くもの
” 美学は「いかに人はよりよく生きれるのか」という問いから誕生した哲学の一領域です。
人間教育の一部として組み込まれている学問であり、この世界におけるあり方、佇まい、思考、所作に深い影響を与えます。 ”
この 真美研究所では、美を探究することを通して、感性と思考のアプローチから「美的知性」を磨いていきます。
なぜ、美を探究するのか?
美を探究することにより、美を「感受する力(感性)」はもちろんのこと、「正解のない問いに挑む力(思考)」が育めるからです。
美学は「いかに人は、よりよく生きられるのか」という問いから誕生した哲学の一領域です。この世界におけるあり方、佇まい、思考、所作に深い影響を与えます。
しかし、現代社会ではより広義な意味を持つようになりました。
それは、ファッション、芸術、音楽、街並みや建築、プロダクトデザイン、企業デザイン、さらには、経営マネジメントなど、さまざまな分野に息づいています。これは、美の特異性にあります。
例えば、花を見て美しいと感じる気持ちは、私たちの感性が受け取るもの、すなわち主観的に「感受されるもの」です。
しかし、芸術作品などがそうですが、同時に万人にとって、どの花が最も美しく感じるかという問いも想起されます。そうなると、美の感受は、客観的に「判断されるもの」(普遍性が競われて判定されるもの)とも言えます。
感性的な主観性と判断の普遍性は、ふつうは二律背反的であって両立不可能なものですが、美の感受はどこまでも主観的なものでありながら、同時に客観的な性質も併せ持つということ。
つまり、両立不可能なものを可能にする。これが美の持つ特異性です。
これは、どんなことを意味するのでしょうか?ここまで読んで、勘の良い方はピン!ときたかもしれません。
詳しくは、今後 「真美研究所」内で、お伝えしてまいります。
探究する美とは?
ここで扱う「美」は、美容やアパレルといった業界にありがちな「美醜」という二項対立で語られるような相対的な美ではありません。
企業研修や自己啓発の業界で語られる、美意識や美しいあり方、というような美でもありません。
真知の探求としての美学は、哲学、美学、文学といった形而上にフォーカスしたすべての人文知を駆使して美の本質にせまるあり方です。
哲学や科学をはじめとする過去の全知が探求してきた真理、あるいは絶対性の象徴としての神や悟り、そのすべてを集約した「普遍的な美」です。崇高ささえも感じられる美であり、人の心をうつ美です。
その美は、世界や人間という自分の外側を構造的に捉え、そこから演繹的に思考するという「美的思考」を持ってして初めて語りうるものです。
そして、美的思考を持って「美しさとは何か」を考える機会を持つことは、美しい生き方、人格と教養の形成に繋がると考えています。

「美」へのフォーカスによって何が得られるのか?
ビジネスで結果を出されている方や高い視点で物事を見る力のある方は、既に気づいていらっしゃると思います。
これはもう紛れもなく「ビジネスセンス」です。
実際、世界で活躍する真の成功者、有力者、実力者は、俳句を嗜んだり、美術館や音楽会などに足を運び、文学や芸術など形而上の世界に触れ、感性を磨くことを大切にしています。
これは、なぜでしょうか?
美について考えることは、一見ビジネスや実利に全く関係のないことのように感じるかもしれません。しかし、普段自分がどのようなものに触れ、感性を磨いているかが「生み出すものの質」を決めているかを深く理解しています。
自分のものの見方が変われば、世界や人間の捉え方が変わり、発想も変わってくるからです。
多くの人は、目に見えるわかりやすいものに飛びつきます。しかしそれらは、全て枝葉にすぎません。すべての物事の裏側には、一見すると「目に見えないものの本質」が常に存在しています。
すべての「目に見えるもの」は、何らかの「目に見えないもの」が変換され生み出されたものだからです。
ここで扱う「美学」は、最高抽象度の知。すべての根幹となる「源の知」であり、すべてのモノコトはこの知から生み出されます。
その一番上が変われば、一気に「知」の形が変わることは容易に想像できるでしょう。
また、哲美文といった形而上にフォーカスし、美の本質にせまるあり方は、科学偏重時代において、科学や実学など、実利重視の学びから逃れた、純度の高い「真の知性」に出会えます。
数年前に『なぜ、世界のエリートたちが美意識を鍛えるのか?』という本が売れました。
経営者や上層部の人たちは、早い段階からそのことに気づき、美にフォーカスしていたのです。
こうした高い視点から美的思考を持ち、考える機会をもつことは、ビジネスをしている人であれば、出会う人の質を変えていくことに繋がります。
「美」の無限性
「美」の探究の面白さは、成長に応じて「受け取り方が変わる」というところにあります。人格・教養により、無限に成長できるのが「美」なのです。
「意識の変革をもっとしていきたい」「より質の高いレベルへ行きたい」と思うのであれば「真美」の探求が最適です。全てにおいて「質」が磨かれていく。つまり、真の「美意識」が磨かれるからです。
もちろん、そうした「美」を探究する研究員として、ビジュアルの面での「表現力」も実践で磨いていきます。
日本人の精神性
”やまと歌は人の心を種(たね)として、よろづの言(こと)の葉(は)とぞなれりける”
これは古今和歌集の仮名序の冒頭に書かれた紀貫之の言葉であり、日本人による最初の自覚的な芸術知として位置づけられています。
そしてこの歌には、西洋世界が渇望する真美、普遍美、絶対美、客観美が秘められています。
彼ら西欧人がその象徴として、長らく畏敬の念を持つ対象。それが、日出づる国、日本なのです。
長い伝統と歴史の中で培われ、受け継がれた日本の精神性。
しかし、その日本美学は、確固とした教育に組み込まれておらず、むしろ衰退の一途をたどっています。
日本人の教養の低下は、国際的な競争力の低下にも繋がり、国の未来に大きな陰を落とすでしょう。
この問題に対して、私たち 東京官学支援機構(TASO) ができることはないかと考え、立ち上がったのが 東京美学倶楽部 です。
「先人たちが切り拓いた日本特有の美学を、ともに学び、考え、伝える力を身につける場を提供する」

社会貢献と事業収益の両立
「真美研究所」では、世界のアカデミズムに裏打ちされた真の美学を提供いたします。
弊社は、社会貢献と事業収益を両立すべく、学術研究支援の事業団体である東京官学支援機構の理事、東京美学倶楽部の上席研究員としても活動しています。
具体的には、中央官庁所管の行政法人、公益法人、国立大学法人等の諸活動を支援するとともに、最新の研究内容に触れ、アクティブラーニングを通じて思考を深め、リベラルアーツの研究に係る国策の情報収集や分析、発信などの活動を行っています。
この真美研究所で扱う情報は、協力機関である東京官学支援機構(TASO)とTASOが主催する人文知普及と研究の会員制サロン東京美学倶楽部の資料をもとに作られております。
東京美学倶楽部は、最高学府と関わってきた経緯と実績を土台として、東洋知にも西洋知にもとらわれない日本知、メタアカデミズムを志向しています。
メタアカデミズムは、あくまでもアカデミズムとの関わりを経由して辿り着いた領域です。
現在、国が認めている人文知(西洋哲学やリベラルアーツ)から、日本の未来のために国が庇護すべき真の人文知へ。
日本特有の美学、真美の探求のあり方を、共に学び、考え、伝える力を身につける。
この使命の元に東京美学倶楽部は存在しています。当「真美研究所」の活動もその一環です。
なぜ、こうした活動を行っているのか?
日本の未来のために。
世界の中で、日本の存在感や発言力をより高めていくためには、日本の人文知を支え、伝え、学ぶことが重要だと考えています。人文知とは、文学、哲学、歴史、芸術、言語、文化など、人間が創り出した知的・文化的なものを指します。日本の人文知は、世界に誇るものが多くあります。例えば、日本文化には独自の美意識や倫理観があり、それは世界中で高く評価されています。
日本の歴史は長く、多様な文化的交流があり、そこから得られる知識や知恵も豊富です。これらの人文知を支えるためには、教育や研究の場を充実させることが必要です。特に、人文科学分野の研究は、短期的には経済的な成果が得られにくいため、長期的な視野で支援することが求められます。
また、人文知を伝えるためには、文化交流や留学などの国際交流の促進も必要です。日本の文化や歴史を外国人に紹介することで、国際的な理解や協力関係を深めることができます。さらに、人文知を学ぶことは、人間性を育む上でも重要です。
一方で、現在の日本の教育現場では、科学技術分野が重視されがちです。人文科学分野も重要な役割を果たしています。人文知を学ぶことで、豊かな感性や創造力を養い、社会に貢献することができます。以上のように、日本の人文知を支え、伝え、学ぶことが、日本の存在感を高めるために必要なことと考えています。
人文知の普及を推進する組織として立ち上がった東京美学倶楽部で提供される、世界のアカデミズムに裏打ちされた美の哲学を追求する唯一無二の学びを、一人でも多くの方々と共有するため、そして、日本の底力を上げ国際的な存在感を高めるために、「真美研究所」は誕生しました。
考える力を磨く「思考空間」
大人の真の学びとは「教わる」のではなく、自ら「学ぶ」こと。つまり、考えること。思考は思考をすることでしか磨けません。「真に思考する」空間を定期的に設けることにより、本当の「考える力」がつきます。
人は、情報量が多いと、正しい判断ができると思っています。しかし、真逆です。情報量が多くなればなるほど、実は思考力は低下します。
なぜなら情報と比例して考えるべきことが増えるからです。すると、問題が複雑化するため、判断が難しくなるのです。
また、知識として知っていても、体験が伴っていないと本当の意味で知ったことにはなりません。
そのため、「真美研究所(シンビラボ)」では、新しい情報や知識を頭に入れ理解しようとするのではなく、体得重視の実践的な演習を通して学ぶことを大切にしています。
会員募集
美の探究することで、人生や仕事をよりよくしていくことを目的にしています。
こんな方におすすめ致します。
・知性と教養溢れる大人の女性としての美しさを求める方
・詩や文学、日本語の探究に興味のある方
・論理的な思考だけでは限界を感じている方
・新しい着想を生み出す視点を持ちたい方
・抽象的・本質的な学びに価値を持てる方
・人文知普及推進活動に賛同してくださる方
こんな方には向いておりません。
・すぐに結果が欲しい方
・知識を得ることを目的にしている方
・効率や合理性を優先する方
※ご入会は、随時受付ています。期間は、ご入会から1年間となります。
※どの月から参加していただいてもご理解できる内容です。
※保護者の方が会員の場合、中高生のお子様は親御さんと一緒に無料でご受講いただけます。
※学生の方は、学生割引制度をご利用いただけます。詳しくは、お問い合わせください。
「真美研究所」が現在取り組んでいるプロジェクト
受講生の声
■ワークを通して日本語の奥深さに触れ、心が癒されるのを感じます。美しい日本語と日本人特有の感性を持っていることを誇りに思うと共に、後世の人にも伝えていきたいと思いました。
■私は言語化を苦手としています。そこにチャレンジしたいと思い参加しました。 また、自分の価値観でしかモノが見れていないので、いろんな価値観の方と関わりたい。 いつもふみこさんが言っておられる、何を学ぶかも大事だけど、誰と学ぶかも大切だと思っています。 縁ある方たちと切磋琢磨して、美しい日本をより美しい国にしていけたら最高だと思ってます。 そんな思いで学ばせて貰っています。
■いかに自分が見えているものしか見ていないのかに気付かされます。いろんな方の考えを聞いていると、同じものに対しても、そんな考え方やものの捉え方もあるのかと勉強になり、視野が広がります。
■いつも仕事に追われ頭の中が忙しいのですが、ワークを考えている時間は頭の中が静かになります。普段考えないようなことを考えることで、脳の違う部分が活性化されるのを感じると共に、ものの見え方が少しずつ変わってきました。
■日本人でありながら、日本語について知らないことが多く、日本人はこんなに豊かな感性と表現を持ち合わせているのかと驚きました。美しい日本語表現を磨いていきたいと思います。
■抽象度を上げて考える癖がついてきました。方向性を決めるときの発想も今までとは違ってきたのを感じています。
■ワークの発表を通して、それぞれの個性がみえてくるので、それがとても素敵だなと感じます。普段出会わないような方達と一緒に学べることが楽しいです。

メンバーとの岡山研修での一コマ
代表挨拶

東京官学支援機構 理事
東京美学倶楽部 上席研究員
東京リベラルアーツクラブ研究員
三思文学文芸員
比丘尼会 会員
株式会社LuGEND代表取締役
初めまして。真美研究所代表、兼主任研究員の豊田ふみこです。
私は、過去15年以上にわたり、経営者や起業家などビジネス業界をリードする方を対象に、印象を整えるコンサルティングを個人・企業問わず提供してきました。
また、デザイナーとして、ロゴ製作やプライベートブランドの開発支援も行い、ブランドの商品開発・製造販売の経験を通して得た、形而上にある想いを視覚化できる強みをいかし、日々の情報発信やコミュニティでの定期的な知識の共有をしています。
哲学をビジネスに活かす観点から、2021年より女性リーダー向けの哲学講座を開始。同年、東京官学支援機構の理事に就任。以降、哲学、美学、文学にフォーカスした人文知の普及・推進活動に取り組んでいます。
※メルマガでは、美学の視点から「感性と思考を磨くヒント」をお届けしています。
こちらからご登録いただけます。
https://visualimage.jp/mailmagazine/
研究所概要
| 名称 | 真美研究所(シンビラボ) |
| 英文社名 | SHINBI Lab. |
| 運営会社 | 株式会社LuGEND |
| 所在地 | 〒102-0074 東京都千代田区九段南一丁目5番6号りそな九段ビル5階 |
| 代表 | 豊田ふみこ |
| 協力機関 | 東京官学支援機構、東京美学倶楽部 |
| 特別顧問 | 山本雄一郎(東京官学支援機構本部長、東京美学倶楽部主宰、美禅院初代住職) |