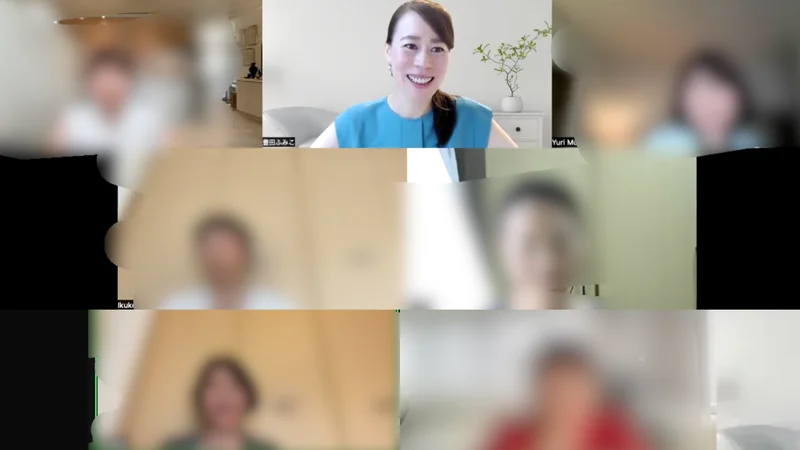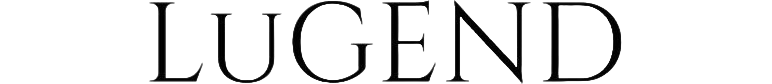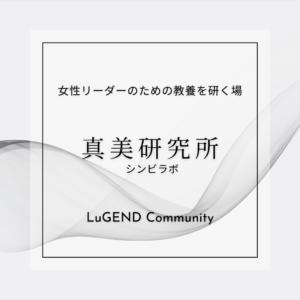こんにちは、真美研究所主宰の豊田ふみこです。
週末は、真美研究所のメンバーと「アートと食をつなぐ」というコンセプトのお店に行ってまいりました。
このコミュニティでは、美の探究をテーマにしており絵画や詩などのアートや文学を通して、感性と知性を磨くことをしています。

内面が外側に現れる
この仕事を始めてから、外見の印象をよくすることや自分のスタイル(軸)を持つ、ということをサポートする仕事をしてきました。
つくづく思うのは、歳を重ねれば重ねるほど内面が外側に現れる、ということ。
その人の暮らしぶりは、姿勢や体型にでますし、その人が考えていることは、顔のクセとなり眉間のシワや口元にでます。
これは、日々の積み重ねで出来上がるものなので、外側をいくらよくしていても土台は隠しきれません。
確かに、年齢を重ねると代謝が悪くなり痩せにくくなって、お腹はぽっこり出てくるし筋力は衰えてくるわで、痩せようと思っても若い時のようにはいきません。
鍛えたり、メンテなしでは、体型を維持するのもなかなか厳しいのも事実です。だからこそ、歳を重ねてからが本番なのかもしれません。
ここからは、自分の身体の手入れをしているか否かの差が生まれてきます。
トレーニングしている方は、たとえふくよかだったり、歳を重ねられていても、肌のハリや筋力が違ったり、姿勢もキレイですから。そんなわけで、私自身、必死にトレーニングに励んでおります。
そういった諸々のことを含めて何を大切にしているかが、結局、見た目の印象となって、現れてしまいます。
そして、身体のトレーニングの中で、忘れてはならいないのは、脳(思考)も含まれます。
脳のトレーニング
今の時代、便利なものにすぐ飛びつく。効率をあげることばかりに躍起になる。そんな風潮があります。
ものごとにひたすら取り組むよりは、便利なものを手に入れて、体裁だけ整えてしまおうとか、知識や情報をかき集めて、なんとか効率よくことを運ぼうそんな生き方が目立ちます。
しかしながら、便利さや効率ばかりを追うと、それだけでは人生というものは味気なくなり、物質的には豊かになったとしても、心は貧しいまま。なにより人として、生きる意味を失ってしまいかねません。
それだけでなく、利便を求めれば求めるほど、脳はその分使わなくて済むから、どんどん衰退していきます。
当たり前ですが、思考は、思考をすることでしか磨けません。
多くの人は、知識量があれば、思考が磨けるかのように勘違いしますが、知識があっても、自ら思考をしていなければ、思考力は身につかないのです。
思考力を磨くには
では、脳を鍛え、思考力を磨くには、どうしたらいいか、というと2つあります。
1つ目が、思考する空間に身をおく。
2つ目が、普段考えないことを考えること。
真美研究所では、この2つのことを取り組んでいます。
このような場は、他にもあるかもしれませんが、大事なのは「何を題材にするか」です。
真美研究所では、真美をテーマに、非言語芸術の「アート」と言語芸術の「詩」を通して、「感性」と「知性」を研く場を設けています。
非言語と言語の境界線を行ったり来たりしながら、「感覚」と「知識」ではなく「感性」と「知性」を研く。
こうした美について考えること、詩や絵に触れること、これらの知的体験は、人生に美しさと豊かさをもたらします。
非論理の領域の大切さ
ビジネス的な観点からいうと、近年、美意識の水準が個人や企業の成果を左右すると言われるようにもなりました。
多くの方がなんとなく気づき始めているのです。
芸術やアートなどクリエイティブな領域に限らず、ビジネスにおいても、学問においても、人生においても、非論理の領域が大切であるということに。
ですが、この領域は、簡単に「理解」できるものではなく「体験」を通して体得するもの。時間がかかるのです。
ですから、いち早くそこに着目し、取り組んでいるのが真美研究所です。