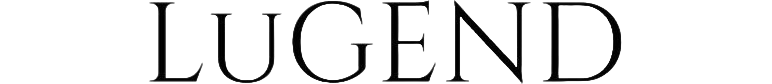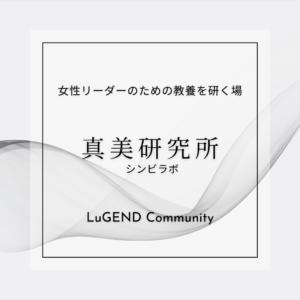こんにちは、真美研究所主宰の豊田ふみこです。
その昔、哲学は世界と人間の本当のことを探求していました。これは、あとから分派的に現れた科学という学問も同様です。
哲学が本当のことを創造し、科学がそれを証明するという役割でした。哲学も科学も、真摯に世界と人間の分析に向き合ってきました。
看破されたテーマ
そんな中、最大のテーマである「真善美」のうち、ニーチェによって「真」と「善」の本質が看破されました。さらに、ウィトゲンシュタインの登場により、哲学や科学そのものを哲学するという流れも生まれました。もはや世界と人間の分析ではなく、分析の仕方の分析であって、そこに世界と人間はありません。
ただ、ウィトゲンシュタインは、あくまでも語りうるものとそうでないものを分けただけでした。世界と人間、あるいは唯一残された「美」、その存在や探求自体を否定したわけではありません。
しかし、彼以降の哲学者はそのことを誤解したまま突き進み、結果、相対化に陥った現在の哲学の姿があります。当然ながら現実の世界と人間のあり様もまた、そうした知の構造の影響を演繹的に受けています。

意志を継ぐ者
一方で、太古の昔から語られてきた言葉があります。
「必ずや私(あるいは神)の意志を継ぐ者が現れる」
誰もが無意識的にソクラテスの登場を待ち望んでいる現代において、科学や哲学や文学を、現代の米国や中国や欧州に重ねるならば、日いずる我が国こそ、その役割を担うべき者とは言えないでしょうか。
実際、武家や商人の力が強大化する中、その規模を縮小しながらも、日本の朝廷や皇室の存在は脈々と受け継がれてきました。
日本こそ真美の象徴であり、私たちこそ「意志を継ぐ者」として、規模は小さくとも矜持を抱いて、美学を探求していきたいと考えています。